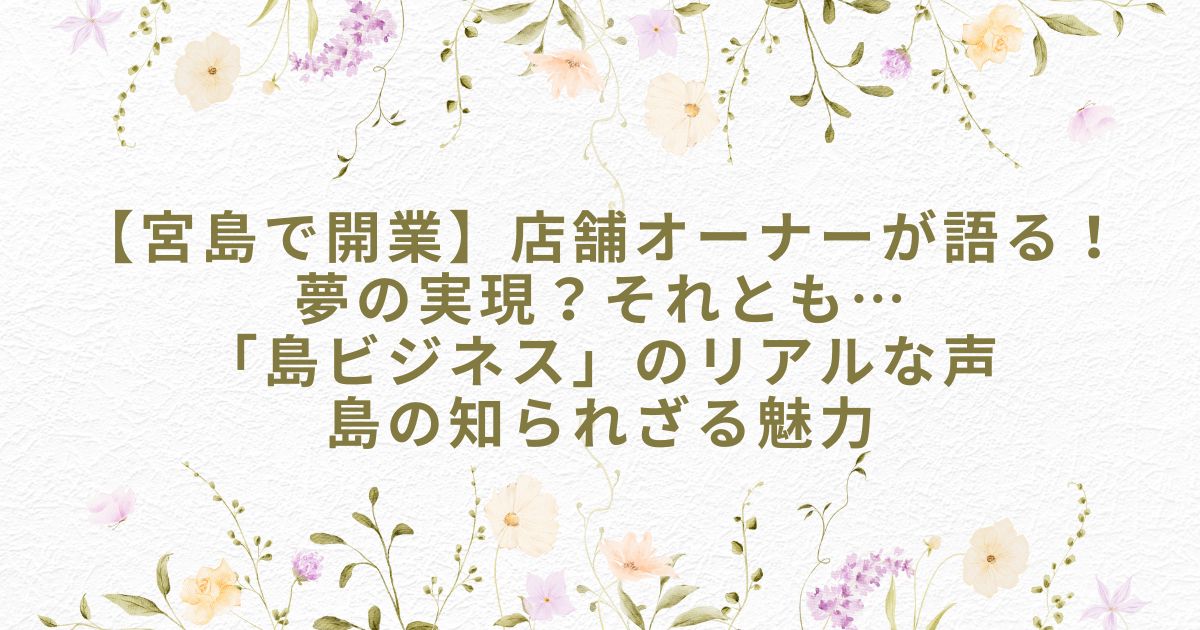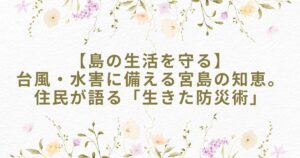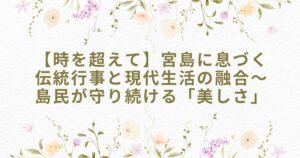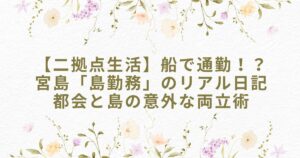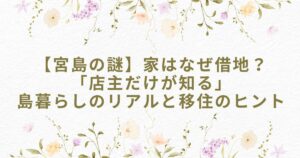私は転勤族として日本の様々な都市で生活してきましたが、宮島で新しい店舗や建物を作る際の難しさは、他の地域とは比べものにならないことを知りました。
条例や景観への配慮が徹底されていて、建築の計画から許可取得、さらには住民との調整まで、とても慎重に進めているのを間近で見て驚きました。
もしかすると、観光に訪れた人や他の地方で住んでいる人は、こうした“建築の大変さ”なんて考えたこともないかもしれません。
でも、宮島は特別な場所なんです…この気づきを実感してもらえたら嬉しいです。
宮島開業の第一関門:厳格すぎる景観条例
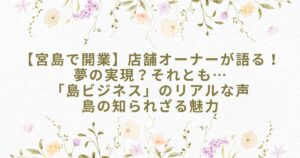
細かすぎるルールに驚愕
宮島で店舗を開業する際の最大の壁が、景観条例の厳格さです。
建物の高さ、外壁の色、屋根の材質、看板のデザイン、さらには緑化の程度まで、すべてが細かく規定されています。
「普通の商業地区の感覚で計画を立てると、確実に行き詰まります」と語るのは、実際に宮島で開業したオーナー。
当初想定していた外観デザインから、3回も設計変更を余儀なくされたそうです。
許可申請に潜む時間の罠
一般的な飲食店の営業許可は2〜3週間で取得できますが、宮島の場合は景観に関する審査も加わるため、計画から営業まで1〜2ヶ月かかることもあります。
さらに、書類の不備や追加協議が発生すれば、その期間はさらに延びることも。
オーナーが語る「人とのつながり」の重要性
いきなりの物件取得は無謀
宮島で開業したオーナーは、みんな「人とのつながりがとても大事」と話します。
最初から物件探しや契約に走るのではなく、地元の人や移住者、行政の担当者と関係をつくることから始めるのがポイントです。
現地に足を運び続ける覚悟
「何度も宮島に足を運んで、島の人たちと話しながら空き家情報を教えてもらったり、協力者を探したりしました。こうして少しずつスタートできました」
実際に開業した人は、「自分で課題を見つけて行動すること」「現地で人と会い、信頼を得ること」が大切だと感じています。
観光客ではなく、島の仲間として認められるには、時間も根気も必要です。
住民との調整は必須項目
宮島は世界遺産の島なので、地元の人は外資系ホテルや大手チェーンの進出にもとても慎重です。
個人でお店を始める場合も、地元住民や行政との話し合いがとても重要になります。
開業前に覚悟すべき「島ビジネス」のリアル
「顔が見える調整」が生命線
物件を取得したり、改装工事をしたからといって、すぐに開業できるわけではありません。
自治体や地元住民と“顔が見える”形で何度も話を重ねることが必要です。
こうした調整はただの手続きではなく、島の仲間として受け入れてもらうための重要なステップです。
営業スタイルまで問われる配慮
宮島では、伝統や景観を大切にする文化が根強いので、お店の外観だけでなく営業方法そのものにも気を配る必要があります。
「何をやるか」だけでなく、「島の日常や暮らしに馴染めるかどうか」がとても重要なポイントです。
開業後に待つ島特有の課題
観光の波に翻弄される売上
宮島のお店は、観光シーズンの忙しさとオフシーズンの静けさの差が本土以上に大きいです。
ゴールデンウィークや紅葉の時期には行列ができるほどですが、冬場はお客さんがほとんど来ない日もあります。
物資調達の困難さ
食材や備品の仕入れも、本土とは全く勝手が違ってきます。
船の運航状況に合わせて配送を工夫したり、天候が悪いと物が届かないこともあるため、毎日の営業に直接影響が出ます。
まとめ:夢と現実の狭間で
宮島で店舗を開業するには、景観への配慮、地域との調整、地元の人々との信頼関係づくりなど、さまざまな壁を乗り越える必要があります。
理想の実現には、多くの時間や苦労も。
ただ、その壁を乗り越えて島で事業を続けているオーナーたちは、「宮島でお店を持つことは、地域の一員として暮らすこと」と語り、充実した表情を見せています。
宮島は、ただ商売をするだけの場所ではなく、地域社会と共に過ごしていく特別な場所です。
夢に向かう前に、まずはその覚悟があるかどうか、自分なりに考えてみることが大切かもしれません。