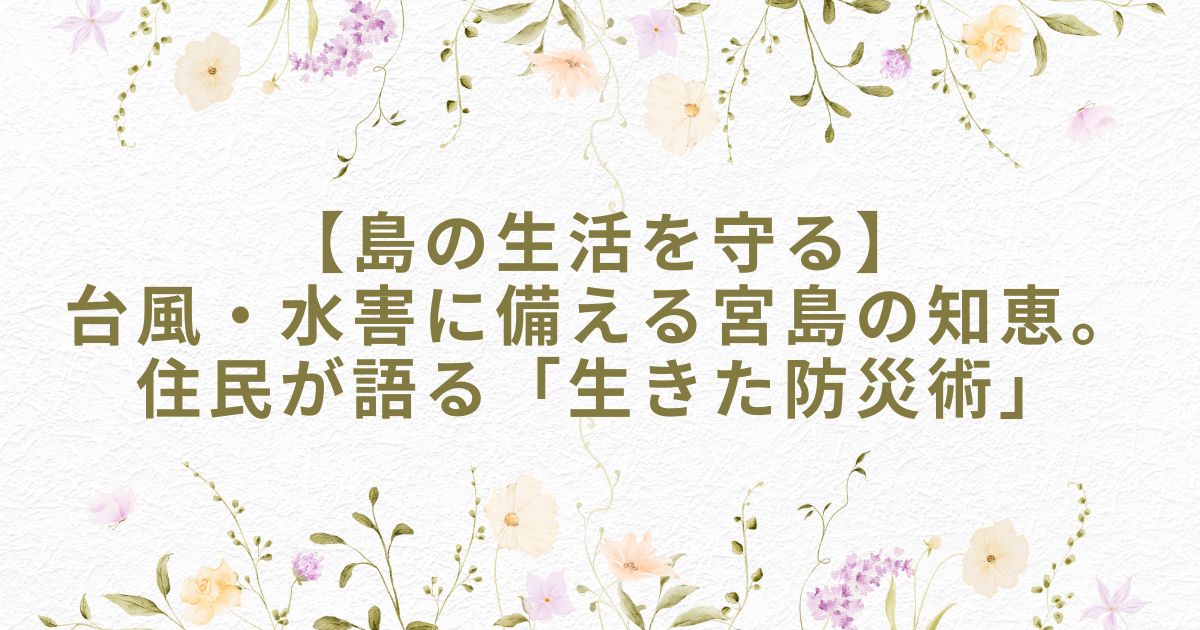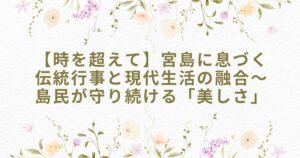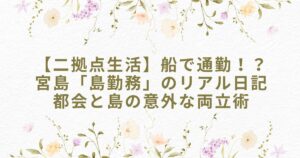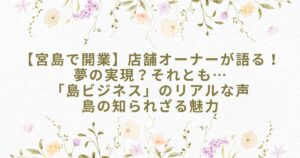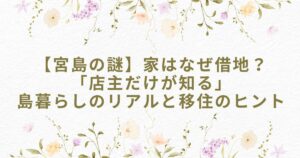世界遺産・厳島神社で知られる宮島。
台風や豪雨が近づくと、住民と神社が力を合わせる“生きた防災術”が今も息づいています。
瀬戸内海の自然条件は厳しいものですが、長年培われた知恵と最新の防災技術が、島の暮らしや文化財を守り続けてきました。
私自身が数年前、広島で暮らしていたころ、台風シーズンになると必ず宮島の町や厳島神社の防災準備が地域ニュースで大きく取り上げられていました。
島の住民たちが総出で土のうを積み、神社の職員が丸太や支柱で建物を補強する様子…島全体が備えている光景は今もはっきり記憶に残っています。
住民が実践する暮らしを守る知恵
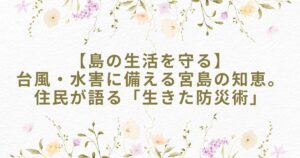
事前準備の徹底が命を守る
宮島の商店街でお土産屋さんを営む田中さん(仮名)にお話を伺うことができました。
「台風シーズンが始まる前から、島の住民は皆、入念な準備を始めるんです」と教えてくれました。
最も重要視されているのがハザードマップの活用です。
住民の方々は浸水リスクや土砂災害の危険箇所を家族全員で確認し、複数の避難先と避難経路を事前に決めているんだそう。
「非常持ち出し品の準備は当たり前。飲料水と食糧は最低3日分、常備薬も忘れずに準備します」と教えてくれました。
島ならではの危機意識の高さを知ることができ、私自身も防災対策の知識が増え、勉強になりました。
停電や断水への備えも入念で、携帯充電器、保冷剤、ラジオなどの必需品チェックリストが各家庭で共有されているんです。
地域に根ざした土のう対策
民宿オーナーの佐藤さん(仮名)は「うちは毎年、台風前に玄関や低地に必ず土のうを設置します。伝統ですね」と語っていました。
町内会の土のうステーションがあり、木造住宅対策で四隅や出入口に重点配置、避難ルートの確保も計算されているそうです。
排水路の維持管理で被害を最小化
近くのカフェ経営・山田さん(仮名)は「通りすがりに側溝や排水路をチェックするのが島民の日課」と語ってくれました。
雨後は近隣同士ですぐに清掃に取り組み、感染症・悪臭を防いでいると話していました。
文化財を守る事前補強の工夫
広島のテレビ局では、厳島神社の台風対策について放送していました。
番組では、台風が接近するたびに神職や職人たちが伝統的な準備作業を行う姿が紹介され、丸太や支柱を建物の外壁に立てかけて補強したり、取り外し可能な床板を外したりする様子が映されていました。
これらの工夫は、数百年にわたり受け継がれてきたもの。
さらに、土のうを積み上げ、神社全体の防御力を高めるよう工夫されています。
回廊や能舞台では、風の通り道を確保するために鏡板を外す方法も用いられ、「先人たちの知恵が今も活かされている」と伝えられました。
こうした住民の日々の備えとともに、世界遺産・厳島神社では独自の防災術も進化している印象を受けました。
長年の経験から、「丸太や支柱による補強」「取り外し可能な床板」「可動構造の回廊や能舞台」「被害部材の迅速な回収と復旧」など、防災と文化財保護の両面を意識した伝統的な仕組みが培われてきたそうです。
島民、神職、技術者が一体となった取り組みが、今も続けられていると紹介されました。
実際、平成16年の台風18号の際は一部で損傷が発生したものの、多くの回廊や能舞台は迅速に復旧し、わずか数日で観光客の受け入れを再開できたという例もあります。
修復・復旧に重点を置いた対応
テレビ番組では、文化財を守る難しさについても紹介していました。
「災害から厳島神社を完全に守ることは困難なため、修復と復旧を重視した対策を取り入れている」と解説しています。
景観や歴史的価値を保ちながら、被害が出た際には素早く部材を回収して修復に活用するなど、バランスの取れた保護と防災活動を続けているそうです。
「文化財の保護と防災、その両方が等しく大切」という点が番組の中でも強調されていました。
実際に、平成16年(2004年)の台風18号では被害が発生しましたが、関係者の連携と迅速な作業によって、わずか数日で観光客の受け入れが再開されるほど復旧が進みました。
この復旧の早さ、そしてこれまで何度も大きな自然災害を乗り越えてきた背景には、住民や神職、専門家たちが協力し、島全体で“生きた防災術”を磨き続けてきた歴史があるのだと思います。
地域の絆が支える総合防災
住民同士の連携体制
老舗旅館の従業員の方は、「台風が来ると分かったら、古民家街の住民同士で声をかけ合うのが当たり前なんです」と、地域の連携について興味深いお話を聞くことができました。
浸水リスクの高い地区では警戒体制を強化し、独居高齢者の安否確認も組織的に行っているそうです。
インフラ強化への取り組み
地元の建設会社で働く方は、「宮島は離島だから、送水管や排水インフラの強化が本当に大切なんです」と教えてくれました。
年間数百万人の観光客を迎える島において、断水は住民生活だけでなく観光事業にも深刻な影響を与えてしまいます。
送水管・排水インフラの二重化、御手洗川水系の耐水化・清掃・長寿命化と地域ぐるみでの総合的な防災を進めていると話していました。
まとめ
宮島の防災術は、住民と神社に脈々と受け継がれる経験と知恵の集大成です。
伝統技術と現代の備えを組み合わせることで、台風や水害に負けない地域の力を築き上げてきました。
「土のう設置」「排水路清掃」「住民同士の声かけ」――日常の積み重ねと強い絆が、いざというときの防災力として発揮されています。
厳島神社の文化財保護と防災の両立は、全国にも参考になるモデルだと思います。
この島で聴いたリアルな体験談や工夫から、防災の本質と地域の誇りを、強く感じることができました。