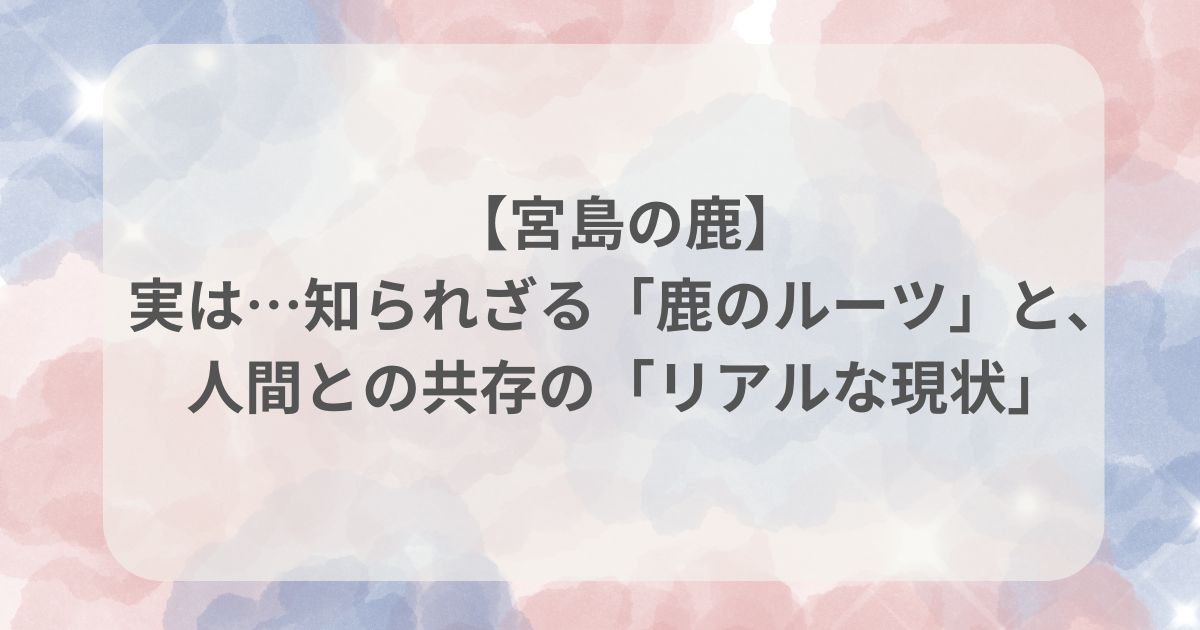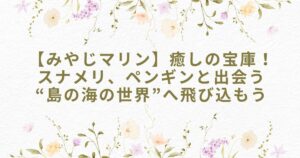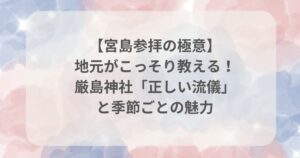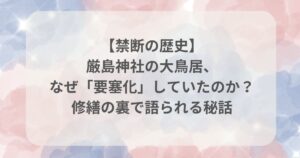広島県宮島の鹿は、多くの人が想像する「奈良公園の鹿」とは全く異なる存在です。
神の使いとして古くから親しまれてきた宮島の鹿ですが、現在は野生動物として扱われ、行政による餌やりも禁止されています。
しかし餌不足による問題が相次ぎ、ボランティアによる給餌活動が鹿の命をつないでいるのが現状です。
観光地としての美しい宮島の裏側には、人と野生動物の共存という現代的な課題が潜んでいます。
宮島の鹿の特殊性 奈良との決定的な違い
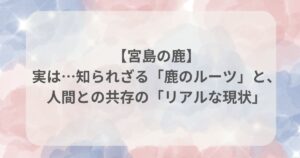
血統から異なる宮島固有の鹿
宮島の鹿は遺伝学的にも対岸の広島・山口地域の固有種で、奈良の鹿とは全く異なる血統であることが判明しています。
古代から宮島で自然発生・定着したと考えられており、戦後にわずかに奈良から追加個体が持ち込まれた記録はあるものの、ほとんどは宮島在来の鹿です。
奈良公園の鹿が国や県、市によって管理され、しかせんべいなどの観光餌やりが観光文化として確立されているのに対し、宮島の鹿は基本的に餌やり禁止となっています。
しかせんべいも存在せず、観光客の不用意な餌やりは推奨されていません。
野生動物としての位置づけ
宮島の鹿の最大の特徴は、人間が管理している奈良公園の鹿と違い、基本的に野生動物として扱われていることです。
行政による給餌も原則として行われておらず、現在は野生動物として自然のまま管理し、給餌をやめて山へ誘導する方針が取られています。
体格も奈良の鹿より小さく、泳ぎが得意で紙製品を狙うなど、生態にも独自性が見られます。
これは宮島という島環境に適応した結果なのかもしれません。
行政の給餌禁止方針とその背景
軋轢解消を目指した政策転換
過去には観光目的で市街地に多く生息し、行政や住民の餌やりも日常的に行われた時期がありました。
しかし鹿が増えすぎ、糞害や農作物被害が深刻化したため、行政による給餌は2007年頃に禁止されました。
鹿が人間の餌やりや過度な接触に慣れると、荷物を荒らしたり、ゴミや紙を狙ったり、市街地で凶暴化するなど人との距離感が壊れ、トラブルへの発展率が高くなります。
人工的な食べ物であるお菓子やパンは、鹿の消化機能では負担になり、健康を損ねるリスクも大きいのです。
生態系保護の観点
鹿が人から餌をもらうことに慣れてしまうと、自分で餌を探す力が弱まり、個体数が過剰に増えたり、生態系のバランスが崩れるリスクを生じさせます。
2007年以降、廿日市市と広島県は鹿を野生動物とし、餌やり禁止や自然の山への誘導対策を行ってきました。
また、給餌による人間依存は鹿本来の生態を損なうだけでなく、島の生態系破壊や伝染病リスクも増加する――こうした点について専門家も警鐘を鳴らしています。
ボランティア給餌活動の実態
「いつくしか」を中心とした支援ネットワーク
行政が給餌禁止の方針を打ち出した一方、餌資源が乏しいため、一部の鹿が飢えるケースも見られます。
そのため、現地ではボランティアが定期的に餌を提供し、鹿の命をつなぐ活動が続いています。
「いつくしか(Itsukushika)」と呼ばれる民間の有志グループや個人を中心に、毎週現地で給餌が行われており、活動の継続で痩せ細りや亡くなるリスクが減少してきました。
代表メンバーの岡本貴晶さん、16年以上活動を続ける米田さんご夫妻などが、協力して宮島の鹿を支えています。
活動内容と支援体制
毎週日曜日を中心に車で宮島へ渡り、鹿がよく現れる20カ所以上でチモシー、ラビットフード、コメヌカ、野菜などの餌を手分けして配給しています。
支援物資は全国の有志やSNS経由で集めた寄付・物資でまかなわれ、現地住民のほか全国の動物・自然保護に関心のある約1000人以上の支援者がいます。
活動記録や鹿の実情はブログやInstagram、SNS、YouTubeで随時発信されており、現地で餌やりを行う人と物資支援・情報拡散・署名活動などで協力する人に分かれて活動しています。
行政との微妙な関係
行政は給餌禁止のお願いを出していますが罰則はなく、ボランティアの地道な活動で命をつなぐ状況です。
給餌活動は合法範囲で行われており、鹿を野生に戻すという理念を基本にして活動されています。
神聖と現実の狭間で揺れる宮島
信仰の対象から現実的課題へ
宮島の鹿は神の使い(神鹿)として古代から尊ばれてきた歴史があります。
昔は厳島神社でも神鹿として銅像を建てたり飼育苑を作った歴史もあったそうです。
しかし近代以降、寄生虫や軋轢、環境破壊、個体数増加が問題になりました。
島の信仰・民俗的には鹿は神聖な存在ですが、現代の観光・住民生活・環境政策では問題回避のほうが優先される状況になっています。
神聖視して大切にするという想いだけでは、実際の生活や自然とのバランス維持はできず、あえて餌やり制限が行われているのが現状です。
続く模索と議論
農作物やゴミの食害、糞などで人との軋轢も多く、共存できない現実があります。
野生の管理が難しいこと、人と鹿の距離感調整が極めて難しい問題なのだと感じます。
ボランティアや一部住民が命を守る努力を続けている一方で、適切な個体管理と地域景観・観光とのバランスが課題となっているようです。
宮島の鹿は野生・固有種として、行政主導の餌付けは行われておらず、住民やボランティアの負担と善意で共存体制が保たれているのが現状です。
まとめ 現在進行形の問い
宮島の鹿問題は、奈良公園のような餌やり文化とは全く異なり、野生性と命の現実をどう対応すべきか今も問われています。
生態系・人間生活・観光が交錯した複雑な現代の島で、鹿との距離感を模索し続けているのが実情です。
宮島の鹿は、私たち人間が自然との付き合い方、いのちとの向き合い方を考え直す現在進行形の問いを投げかけ続けている存在なのだと思います。